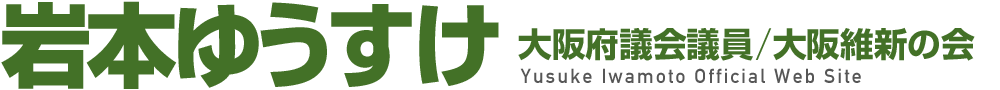令和7年8月6日、大阪維新の会府議会議員団は吉村知事に対し、大阪府施策についての提言をいたしました。
岩本も政調役員として、主に総務常任委員会分野で作成にかかわらせていただきました。当日も、重点項目である(1.日本の成長エンジン都市・大阪)のうち、 (1)万博後の大阪の未来に向けたBeyondEXPO2025の策定について発言をしました。以下、提言の全文を掲載します。
はじめに ~ 世界の叡智を結集し、多様な価値観と共に いのち輝く未来を切り拓く大阪 ~
今年4月に開幕した2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)は、1,400万を超える人々が来場し、会場で披露されている新たな技術や世界各国の先端技術、地域産業、文化等に触れた。万博に参加した児童・生徒は、命の尊さや持続可能な社会、未来社会の技術を肌で感じることで、自ら主体的に考え、行動するきっかけになったと評価してる。
現在、大阪が直面している課題は、南海トラフ巨大地震への備えや府域各地のバランス取れた成長、教育現場の改革、困難を抱える方々への支援、そして共生社会の実現など多岐にわたる。これらを解決するため、国境や文化の垣根を超えて世界中から大阪に集まるテクノロジーやアイデアを共創の資源として活用し、社会課題を乗り越えていかなければならない。課題解決を通じて、若い世代の探究心や共感力、創造力を醸成し、未来を担う人材の育成に注力することも重要である。そして、府の施策を世界に向けて発信し、多くの人に伝える取組も不可欠だろう。
いのち輝く未来社会の実現に向けて、ヒト・モノ・投資を世界中から呼び込む持続可能な好循環を生み出し、日本の成長を牽引する大都市として大阪が発展し続けることができるよう、本提言を取りまとめた。この内容が、府政の施策に着実に反映されることを強く願い、所属議員の総意として要望する。
(目次)( ★マークが今年度の重点項目)
1.日本の成長エンジン都市・大阪
(1)万博後の大阪の未来に向けたBeyondEXPO2025の策定 ★
(2)首都機能バックアップの早期実現と大阪南部地域の強みを活かした災害対応力強化等の取組 ★
(3)南大阪における地域課題解決に向けた成長産業の創出と地域活性化 ★
(4)基礎自治機能の充実強化
(5)大阪広域データ連携基盤(ORDEN)の横展開と自治体間での共用化
(6)府市統合案件の今後のあり方検討
(7)財政運営のあり方
(8)法人府民税・事業税の課税のあり方
(9)BeyondEXPO2025実現に向けた組織構築や人事制度
(10)関西国際空港の機能強化と地域の発展
2.成長し続けるグローバル都市・大阪
(1)国際金融都市OSAKAの推進と府民の金融リテラシー向上
(2)世界に誇る大阪IR実現に向けた取組と観光分野の基幹産業化
(3)府域一体となったスーパーシティ実現に向けた取組強化
(4)大阪の観光資源を生かした観光振興の取組と宿泊税の適切な運用 ★
(5)観光振興を推進するための財源確保
(6)歴史的資源や観光映像を活用した観光振興の取組
(7)民泊の実態調査と厳格な制度運用による指導啓発
(8)再生医療の成長産業化に向けた戦略的な取組
(9)万博後の大屋根リングの保存
(10)大阪広域ベイエリアのまちづくり推進
(11)大阪港湾の戦略的な土地活用の方針
(12)大阪府都市基盤施設長寿命化計画の着実な推進
(13)空飛ぶクルマの商用化に向けた取組
3.子ども輝く未来創造都市・大阪
(1)児童・生徒が自ら主体的に考え、行動する取組の推進
(2)実効性のある府立高校改革アクションプランの策定と着実な実行 ★
(3)学びの多様化学校の公私連携
(4)校内支援ルームにおける適切な人員配置
(5)児童・生徒への自殺対策
(6)学校現場でのギャンブル等依存症に対する意識調査と情報周知の徹底
(7)教職員間のハラスメント事案への対応体制の強化
4.誰もが健やかに暮らせる健康寿命都市・大阪
(1)困難な状況にあるこどもや女性、性暴力被害者に対する支援体制の強化 ★
(2)重大な虐待ゼロに向けた児童福祉行政の水準向上
(3)待たせない診療体制に向けた児童精神医療の体制拡充
(4)「大阪依存症センター(仮称)」の早期立上げと支援情報の発信強化
(5)医療的ケアを必要とする障がい児者、重度障がい児者への支援の拡充
(6)障がい福祉サービス事業者に対する運営指導体制の強化
(7)主任介護支援専門員更新研修の受講要件の緩和
(8)がん予防の取組推進及び医療体制の充実と支援
(9)物価高騰の影響を受ける府民への支援
(10)府営住宅への子育て世帯の入居促進
(11)エスカレーターの安全利用に向けた取組
5.犯罪のない災害・有事に強い安心安全都市・大阪
(1)災害対応の効率化・高度化に向けた防災DX・新技術の活用 ★
(2)地域防災における多様な防災人材の地域実装と市町村支援体制の強化
(3)被災者の「命をつなぐ」ための災害応急対策
(4)ブロック塀一般についての安全対策
(5)「大阪府安全なまちづくり条例」の周知啓発
(6)無許可営業の風営法違反に対する取締強化
(7)自転車等の安全走行に向けた取組
(8)ヘルメットの着用率向上に向けた取組の強化
(9)運転免許更新センターの適正配置と府民利便性の確保
(10)女性警察官に配慮した交番整備
6.産業と自然が豊富で持続可能な都市・大阪
(1)大阪・関西万博を契機としたユニバーサルデザインのまちづくり推進 ★
(2)2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取組 ★
(3)プラスチックごみのさらなる削減
(4)大阪産品のさらなる海外販路開拓の取組
(5)人材不足を補うための戦略的な取組の推進
(6)府営公園のさらなる魅力向上と「持続成長型の府営公園」に向けたあり方検討
(7)万博開催を契機とした都市緑化の推進
(8)単位面積あたりの農業産出額全国1位への取組
(9)都市型林業の推進と大阪産木材の利活用についての取組
(10)大阪オリジナルぶどう「虹の雫」のブランド価値の確立
(11)人と動物が共生できる社会の実現に向けた動物愛護管理行政の推進
以下、提言の本文
1.日本の成長エンジン都市・大阪
(1)万博後の大阪の未来に向けたBeyondEXPO2025の策定 ★
大阪・関西万博は経済の起爆剤と言われ、その経済波及効果や来阪者増による地域活性化、大阪の認知度向上などが期待されている。万博が無事に開幕して賑わいを見せる中、万博後の大阪の成長は府民や各界にとって大きな関心事となっている。万博がもたらす良き流れをしっかりと受け継ぎ、大阪の成長の果実を大阪市域だけでなく府域全域、府民全員が受け取れるような成長戦略となるよう、「BeyondEXPO2025」の策定に向けて以下に提言する。
BeyondEXPO2025の策定にあたっては、万博アクションプランを深化させ、万博で披露されている技術やサービス(例えば、ライフサイエンスやカーボンニュートラル、モビリティといった次世代成長産業等)の実装化・産業化に向け、万博に向けて培ってきたネットワーク等を生かし、産・学・官が強固に連携できる実効性のある取組みを打ち出すとともに、府内の産業集積やインフラの整備等の地域特性を踏まえつつ、AI基盤や国際金融システムの構築を進め、スーパーシティ型国家戦略特区といった規制緩和も活用しながら、府内全域で民のチャレンジを活かす取組を検討すること。
これまでは、大阪市内での取組が重視されてきた。しかし、万博会場でも様々な技術革新に見られるように、今後は通信技術や移動手段が飛躍的に向上し、人々のライフスタイルが大きく変容する。場所に捉われない働き方や暮らしが実現し、人々の価値観も更に多様化していく。次期成長戦略においては、最先端技術の暮らしへの実装化や自然と調和のとれたまちづくりを進めることで、ウェルビーイングの向上につながるものとすること。

(2)首都機能バックアップの早期実現と大阪南部地域の強みを活かした災害対応力強化等の取組 ★
現在、大阪府は副首都ビジョンで掲げる首都機能のバックアップ体制の構築に向け、令和8年度に設置予定の防災庁について、バックアップ拠点が大阪・関西に設置されるよう取組を進めているところである。
一方で、大阪南部は和歌山県など南海トラフ巨大地震のリスクが非常に高いエリアに近接しており、甚大な被害が想定されるエリアに隣接した即応拠点としての立地的な優位性を有する。具体的には、このエリアには阪和自動車道や大阪湾の港湾機能、そして空の玄関口である関西国際空港など、陸・海・空のネットワークが集積しており、南海トラフ巨大地震発生時には人的・物的リソースの集積・輸送・展開が迅速に行えるため、広域支援拠点としての高い機動力と即応性が確保できる。そして、他の大都市圏に比べて大規模用地の確保が可能な希少エリアで、都市としての利便性も兼ね備えている。
そこで、南海トラフ巨大地震の30年以内の発生確率が80%程度に引きあげられた現状も踏まえ、大阪全体ひいては西日本全体の防災力の底上げに資するよう、令和8年度に設置予定の防災庁のバックアップ拠点が大阪に設置されるよう取組を進めること。加えて、国の研究機関等の誘致や既存の防災拠点等との連携も含め、大阪南部地域の強みを活かした災害対応力強化・防災力向上につながる取組の検討を進めること。
(3)南大阪における地域課題解決に向けた成長産業の創出と地域活性化 ★
大阪府では、北部地域と南部地域の間に存在する経済や教育、生活水準の格差が長年にわたって是正されることなく今なお継続している。特に、近年の南大阪地域は、人口の減少・高齢化、若年層の流出、医療・介護ニーズの増大、地場産業の空洞化が進み、公共交通機関の撤退や府立高等学校の閉校などといった社会問題となって顕在化している。
南大阪では、世界に誇る歴史・文化資源や、豊かな自然と大阪産(もん)などの食資源等、多数の魅力的な地域資源がある。さらに、関西国際空港をはじめとする湾岸部における物流・インフラの集積に加え、大阪公立大学や大阪産業技術研究所、大阪環境農林水産研究所などの研究・教育機関、現場密着型の中堅・中小企業などが集積している。例えば、大阪公立大学には、次世代の電池技術として期待されている全固体電池の研究拠点があり、実用化に向けた研究が進められている。また大阪湾ベイエリアの堺泉北地域では、次世代エネルギーである水素やアンモニアをはじめペロブスカイト太陽電池といったゼロカーボン社会に向けた産業拠点の形成が進められている。さらに、南河内地域では、移動の足となる公共交通の確保といった地域の社会課題の解決に向けて、万博で使用されている自動運転バスを活用した社会実験を万博後に予定しているなど、万博のレガシーを継承した取組みも進められようとしている。
このように、南大阪地域は大阪の成長・発展、府民の暮らしの向上に寄与できるポテンシャルを有するエリアであり、今後、大学、研究機関、民間、行政が有機的に連動して未来社会の実装拠点として活用していくことで、農業・観光業の振興はもとより、新産業の創出も期待でき、地域の活性化、定住人口の維持・拡大につなげることができると考える。また、先に述べた大阪南部地域の災害対応力強化によって、防災産業の新市場創出という好機になることも大いに期待する。
現在、府市において大阪の成長戦略となる「BeyondEXPO2025」を策定中であるが、研究機関や大学などと連携して、南大阪でチャレンジする企業の新技術の社会実装化支援やスタートアップ支援等を通じて、新たな成長産業の創出や関連企業の集積を行うなど、南大阪地域のポテンシャルを活かした産業政策や地域活性化策について検討を行うこと。
(4)基礎自治機能の充実強化
大阪府基礎自治機能の充実及び強化に関する条例が制定され、令和7年3月には、基礎自治機能充実強化基本方針が策定された。こうした中、今年度は府域で新たに2つの協議体が設置され、基礎自治体が自らの将来像を描く動きが芽生え始めている。今後は、本基本方針に基づき、市町村へのヒアリングや将来予測に必要な情報提供、広域連携のさらなる促進、自主的な合併への支援など、財政措置も含め具体的な施策を実施していくこと。
また、基礎自治機能の充実強化に関する施策を強力に推進できるよう、大阪府の組織体制の充実と強化を図ること。加えて、府民に対しては、基礎自治機能の充実強化に関する気運醸成や理解の促進に努めること。
(5)大阪広域データ連携基盤(ORDEN)の横展開と自治体間での共用化
行政総合ポータルである「my door OSAKA」の府内市町村の参画数は、現時点で4市が参画(予定)で、共同利用の目的である地域のデジタル格差解消による住民QOL向上や官民の活発なデータ利活用によるイノベーション創出、地域経済の活性化を達成するには、さらに多くの府内市町村に参画してもらう必要がある。しかし、費用負担に対する住民理解やデジタル化導入への庁内調整のハードルが高いといったことを理由に参画が進まないと聞く。
このため、参画にあたっての課題やニーズの聞き取りや、丁寧な説明と周知をあらゆる機会を通じて行うとともに、導入した市町村に先行事例を説明してもらうなど、より多くの市町村が共同利用に向けた検討を進められるよう、積極的な働きかけを行うこと。
また、都道府県間での共同利用については、自治体データ連携基盤共用化研究会等を活用し、共同利用の形態やメリット・デメリットの深堀りをしつつ、共同利用の際に必要な運用スキームやルールの策定に向けた検討を速やかに行うこと。
(6)府市統合案件の今後のあり方検討
広域自治体としてのガバナンス強化は、持続可能な行政の土台である。府市で重複する事業の統合は、単なる効率化にとどまらず住民本位のサービス再構築の契機となる。例えば、水道事業、消防事業の統合は進展が限定的であり、議論に停滞する箇所が存在している。副首都推進本部会議では、未統合領域ごとの課題・論点整理表を作成し、一元化に向けての段階的なロードマップを示すこと。
水道事業の統合は、将来的には府域の全自治体で専門人材の確保等の課題が大きくなることが見込まれることから、府として推進していくことが求められる。何が障壁となっているかの要因を丁寧に聞き取り、必要に応じて国に法改正を求めるなど、必要なアクションを行うこと。
消防事業の広域化は、今春からいくつかの自治体で消防司令センターの共同運用が始まるなど、取り組みが進んでいる地域もあるが、更なる広域化(ブロック化・一元化)について各市町に課題や推進に必要な条件の聞き取りを行い、さらに促進させること。
(7)財政運営のあり方
令和7年度の臨時財政対策債は、制度創設来初めて新規発行額が計上されないことになり、残高は大きく縮減しているものの、財源不足額は依然として巨額である。財政再建に向けた努力にも関わらず一向に府債残高が減らないなど、国による財政運営のしわ寄せを地方が負っている。
国に対して、地方交付税の法定率引上げを粘り強く求めることにより、臨時財政対策債に依存しない持続可能な財政運営を引き続き目指すこと。
(8)法人府民税・事業税の課税のあり方
法人事業税及び法人府民税の超過課税の継続は、府の財政運営と成長戦略の両立をいかに図るかという課題を突きつけている。課税の意義と公平性の再整理を通じて、府民・事業者双方への丁寧な説明責任が必要である。令和8年度の延長論議に向けた評価が必要であり、経済界との意見交換や他府県状況調査等、府内企業に対する説明責任を府として果たすこと。
また、令和8年10月に期限を迎える法人事業税及び法人府民税法人税割の超過課税について、延長の要否を決めるにあたっては超過課税が企業活動に与える影響などの効果検証を行うこと。
(9)BeyondEXPO2025実現に向けた組織構築や人事制度
組織の構築や人事制度は、政策実現の鍵を握る重要な要素の一つである。現在、万博後の成長戦略「BeyondEXPO2025」の策定が進められており、戦略の具体的な施策をスピード感を持って実行するためには、最適な組織再編や配置、人事制度が必要不可欠である。そこで、府職員が万博を通じて培った知見やネットワークを府政に活かせるよう、万博で披露された新たな技術やサービスの社会実装、産業化が進む組織体制を構築すること。
また、急速に変化する現代において成長戦略を着実に実行し、府が副首都機能を担うためには、これまで以上に民間との連携が必要となる。特に、府庁内に専門性が不足しているIT分野等を補うため、研修等を通じた職員の専門性向上や民間企業や専門人材の知見を取り込んだ政策形成や事業の推進を図ること。さらに、一部の部署では外部人材との協働が進められているが、今後は、全庁的な取組として、他の自治体でも見られるようなDX推進や地域課題解決など専門性が求められる分野の副業人材の公募について早急に検討すること。
社会課題が複雑化・多様化する中、行政だけでは解決しきれない領域も増えている。このため、企業や大学等の知見を取り入れ、社会変化に対応した政策を具現化する公民連携の取組について従来の枠組みを見直すなどしてより一層推進し、多様な主体の連携を加速させること。
以上、府域全体の人的リソースを最大限に活用し、万博後の大阪の成長をけん引する戦略的な組織の構築と人事制度を求める。
(10)関西国際空港の機能強化と地域の発展
関西国際空港は、訪日外国人旅行者数の増加等に伴い利用客数が大幅に伸びており、今後さらなる発展が期待できる。当初の目的であった国際ハブ空港化を見据え、年間発着回数30万回に対応したターミナル拡張等ハード整備が行われたところであるが、空港内事業者の人材確保などソフト面の取組にも必要な支援を行うこと。IR開業や首都機能のバックアップ、国際金融都市の実現によるビジネス需要等に応えるため、関係団体や地元自治体の意向も踏まえ、空港アクセスの強化に取り組んでいくこと。さらに、空港と地域の共生・発展に向け、府域の観光振興を促進するため、地域の取組みに対し必要な支援を行うこと。
2.成長し続けるグローバル都市・大阪
(1)国際金融都市OSAKAの推進と府民の金融リテラシー向上
昨年6月に金融・資産運用特区の対象地域に選定され、拠点開設サポートオフィス大阪デスクの設置が実現するなど認められた項目の具現化が進められているところである。引き続き、大阪が有する都市魅力や個性が発揮できるよう、規制緩和や税制措置などの投資環境の整備等を国に対して強く求めること。
また、スタートアップによる新技術の開発や大阪・関西万博で披露された技術・サービスの社会実装支援などを通じてオープンイノベーションの素地を高め、オープンイノベーション促進税制の活用促進を積極的に図ること。金融系外国企業で働く高度外国人材など、多様な人材が大阪に定着するには、教育環境の選択肢と受け皿を整備し、グローバル都市として成熟を図ることが不可欠である。海外在住の高度人材を対象に実施したニーズ調査を踏まえ、新たなスクール誘致を市町村や関係機関等とも連携して進めるとともに、引き続き既存のインターナショナルスクールに関する情報提供等に努めること。
国際金融都市を推進するにあたっては、府民の金融リテラシー向上が重要である。金融経済教育推進機構(J-FLEC)の取組等を活用して、実践的な金融や消費に関する知識の習得や起業家精神を育む金融経済教育を学校等の教育現場で引き続き実施すること。
(2)世界に誇る大阪IR実現に向けた取組と観光分野の基幹産業化
夢洲2期区域マスタープランVer2.0素案が公表された。この案では、サーキット場やウォーターパーク等、民間から提案のあった万博跡地(夢洲2期区域)開発にかかる民間事業者の募集が今年度後半に実施されることや国際観光拠点の形成を推進することが示された。この国際観光拠点化については、隣接するIR(夢洲1期区域)との連動による相乗効果の最大化を図ること。
大阪IRは、大きな経済波及効果や雇用創出効果に加え幅広い産業分野の活性化が見込まれており、日本が観光立国を推進する上で重要な取組である。このため、ラスベガスのような大型のコンベンションや企業のプライベートイベントの誘致、エンターテインメントショーの充実、府域のナイトコンテンツ強化等による24時間観光都市化に向けた検討を進めること。併せて、新たな舟運ルートの発掘・創出事業(兵庫・大阪連携事業)については、兵庫県だけでなく他府県に広げるなど夢洲の地の利を活かした水上交通網の拡充を図ること。
さらに、IR区域整備の意義の1つに、大阪のさらなる成長に向けた観光分野の基幹産業化が掲げられている。その実現に向けた府域や関西・西日本・日本各地への送客機能の充実に加え、大阪観光局(DMO)や他地域のDMOとの連携を深めることで裾野を拡げ、日本観光のゲートウェイを形成し、経済全体への波及効果の最大化を図ること。そして、IRの成功には府民理解が欠かせない。このため、ギャンブル等依存症対策の実効性の確保と府民向けに実施している大阪IR説明会での具体的な説明に努め、一層の理解向上を図ること。
(3)府域一体となったスーパーシティ実現に向けた取組強化
スーパーシティ全体計画では、いよいよ府域全体でのヘルスケアやモビリティ等のサービス実装・提供が本格化する。「まるごと未来都市」であるスーパーシティの実現に向け、スーパーシティの新たなフィールドとなるエリアでモデルとなるスーパーシティ像のさらなる明確化を図るため、実証的調査(モデル調査)や万博後の取組を見据えた最終報告のとりまとめ等を確実に行うこと。
また、府内市町村における行政課題に対して、スーパーシティ型国家戦略特区の成果や知見等を最大限に活用することができるよう、広域行政を担う府として府内の課題把握に努めるとともに関係機関とのプラットフォーム形成を進め、市町村の求めに応じた協議や支援を積極的に行うこと。
(4)大阪の観光資源を生かした観光振興の取組と宿泊税の適切な運用 ★
昨年度、大阪を訪れた訪日外国人旅行者数は約1,460万人でコロナ前の水準を19%上回って過去最高を更新した。さらに2,800万人の来場者を見込む大阪・関西万博の開催により、今年度の国内外からの来阪旅行者数の増加にも期待が膨らむ。このような千載一遇の機会をチャンスと捉え、さらなる誘客や府内全域での周遊の取組を積極的に進め、観光振興による経済効果の最大化と国際観光文化都市としての地位向上、持続可能な観光を目指すサスティナブルツーリズムの実現を図るため、以下に提言する。
府域には、世界遺産に登録された百舌鳥・古市古墳群や大阪と奈良を結ぶ日本最古の官道である竹内街道といった観光資源が豊富に存在する。引き続き、これら資源の修復や保存管理、磨き上げに努めるとともに、地元自治体と連携した誘客イベントや展示会を開催するなどして大阪が持つ観光資源の社会的価値醸成を図ること。また、AIやVRといった最新技術を取り入れたイベントや映画祭の開催、観光映像を活用した魅力発信やPRを行い、旅行者への訴求力を高めること。
人口減少が進む地域では、宿泊や飲食、買物などの観光消費が地域経済を活性させ、雇用創出にもつながる。例えば、南大阪地域は関西国際空港を有し、大阪から京都や紀伊半島へのゲートウェイである。このような地域が持つ特性や交通インフラを最大限に活かし、近隣自治体と連携した広域周遊の促進を図るなど、地域の多様な魅力を活かした事業を企画立案すること。
今年度は、大阪都市魅力創造戦略の見直しの年である。次期戦略の策定に際しては、官民で収集した旅行者の決済データや行動データを分析し、地域ごとの観光資源や周遊ルートの最適化を行いながらエビデンスに基づく戦略を策定して事業実施すること。また、宿泊税を活用する取組については、データを活用して実施効果を検証するなどして地域住民のより一層の理解促進に努めること。
宿泊税の制度改正により大幅な税収増が見込まれる中、税負担のさらなる理解促進を図ることが重要である。今後は、宿泊税活用事業の妥当性や使途の透明性をより一層高めるとともに、第三者機関による実施事業の審査や評価体制を強化すること。
また、各市町村の観光振興の進展状況やニーズに合わせた補助事業を企画するなどして市町村が宿泊税を有効活用できるようにすること。さらに、学生のクラブ活動やサークル活動に伴う宿泊、府民の府内での宿泊は課税免除の対象となるよう検討すること。一方で外国人旅行者数が過去最高を記録する中、災害時の受け入れ避難先等を不安視する声がある。外国人旅行者専用の避難場所の確保について、宿泊税を財源とすることも視野に早急に検討すること。
(5)観光振興を推進するための財源確保
昨年、大阪を訪れた外国人旅行者数は過去最高を更新し、今後も多くの旅行者の来阪が期待される。一方で、観光客の増加は、一部の地域や時間帯等で過度の混雑発生やマナー違反等による地域住民への悪影響、観光客の満足度低下が懸念される。これらの課題に対処するため、観光客の受け入れと住民の生活の質確保を両立した持続可能な観光振興が求められている。
令和7年度大阪府観光客受入環境整備の推進に関する調査検討会議委員の意見でも、今後のオーバーツーリズム発生や公共サービスの利用増大による住民サービスの低下等、問題の未然防止は喫緊かつ重要な課題であり、早期に対応すべきという見解がある。加えて、それらの対策を講じるための財源として、宿泊税だけでなく二重価格や租税についても議論がなされた経緯がある。
大阪の観光振興という観点からは、単に来阪する外国人観光客が増加したから、外国人観光客に負担を強いるということより、大阪が誇る観光資源やサービスを応援してもらうことを目的とするような寄付金制度の構築を府が主体的に進めて欲しい。その寄付額に応じて府内観光や周遊に活用できるバウチャーの返礼といった仕組みを作り、今後の観光振興に寄与する安定財源の確保に努めることも一つの策である。大阪の観光振興をさらに強化するための安定財源の確保に向け、民間や市町村と連携した寄付金制度の構築等を具体的に検討すること。
(6)歴史的資源や観光映像を活用した観光振興の取組
府内には、大阪の発展に重要な役割を果たした川口地区(大阪市西区)に代表される歴史的資源が豊富に存在する。持続可能な観光まちづくりを推進するため、地元自治体とも連携しつつ、これらの価値ある歴史的資源を活用した観光振興に取り組むこと。
外国人旅行者の情報源として、動画サイトに加えて各自治体が制作する観光映像が注目を集めている。そこで、府内市町村や近隣府県と連携して国際観光映像祭の開催に向けた検討を進めるとともに、観光映像を活用した新たな情報発信の方法も検証するなど、国内外へのプロモーションを積極的に展開すること。
(7)民泊の実態調査と厳格な制度運用による指導啓発
民泊は大阪の宿泊施設の不足を補う目的で導入され、多様な宿泊ニーズに対応できるものとして認知・活用されている。一方で、ここ数年、民泊施設の騒音やゴミ出し等による近隣住民とのトラブルが大阪市内を中心に増加し続けており、無許可の違法民泊も問題になっている。こういったトラブルは民泊が集積する大阪市内にとどまらず、市外においても発生しており、心配の声が上がっている。民泊を地域に根付いた持続可能な仕組みとして機能させるためには、利便性と住民の安心・安全を両立する制度設計が不可欠である。
そこで、無許可営業の厳格な取締やプラットフォーム事業者への規制強化、通報窓口の周知徹底、市町村の対応体制への支援等、しっかりとした現状把握と制度の抜本的強化・見直しを含めた適正な運用を求める。
(8)再生医療の成長産業化に向けた戦略的な取組
昨年6月にグランドオープンした未来医療国際拠点「Nakanoshima Qross」は、再生医療・創薬・iPS細胞研究など最先端医療の実用化・産業化に大きな期待が寄せられている。引き続き、未来医療国際拠点の形成を推進するため、万博で関係を築いた国々とNakanoshima Qrossに入居している企業・研究機関とのマッチングを行い海外販路拡大に繋げること。
また、iPS細胞の高品質化や安全性向上、大量生産に係る技術開発支援を行い、早期の実用化を求めること。さらに、研究成果をスタートアップに繋げ、事業化により地域還元が行われるといったエコシステムを確立するため、地元大学や研究機関に技術を還元する企業への支援や成功事例の共有等を通じてスタートアップ企業に支援を行うこと。
(9)万博後の大屋根リングの保存
大阪・関西万博のシンボル的存在である大屋根リングの保存は、万博の理念を後世に伝えるレガシーとなるもので大きな意義を有している。去る6月23日に開催された検討会で大屋根リングを保存・活用する案が示され、8月末までに実務者間での合意を目指すこととなった。まずは、夢洲第2期区域マスタープランにおいてリングの利活用方針を取りまとめ、開発事業者募集では、リング原型に近い形で活用する案を提示してもらえるよう最大限努力すること。
また、これが実現不可となった場合に備え、南西350mのリングの所有形態や改修、維持管理等に係る費用をどのように調達するか、府民の理解が得られるよう検討を進めること。
(10)大阪広域ベイエリアのまちづくり推進
大阪のまちづくりグランドデザインでは、大阪広域ベイエリアのまちづくりについて、大阪湾でつながる市町が有する多様な資源を活かした広域連携や国際競争力の強化を図るエリアとして位置付けられている。中でも、新たな産業集積地として注目されている木材コンビナートの利活用では、淀川左岸線延伸部などの公共事業に伴う発生土の受け入れ先としての可能性も踏まえ、府が主体となって埋め立て事業を推進し、次世代産業の集積拠点として形成を図ること。併せて、各市町村が有する地域資源の活用と民間との連携による観光拠点の創出を通じた周遊性の高い観光施策を推進すること。民間や地元自治体が活用を求める際は、用途規制等の都市計画制限の緩和の技術的支援に取り組むなどし、産業と観光が一体となった戦略的なベイエリアのまちづくりを積極的に進めること。
(11)大阪港湾の戦略的な土地活用の方針
大阪港湾局が所管・保有する広域な港湾エリアは、民間企業による大規模な事業展開により、大阪・関西の経済発展に寄与し、ベイエリアの賑わいづくりに大きく貢献しているところである。
令和3年8月に公表された「大阪広域ベイエリアまちづくりビジョン」では、大阪広域ベイエリアの将来像を示すとともに、ベイエリアの活性化に関わる様々な主体の基本的方向性を示したものであるが、港湾を利用する貨物は、農産物、木材、中古車、コンテナなど時代のニーズとともに変遷してきており、大阪港湾局には、ビジョンを踏まえつつ港湾を取り巻く環境の変化に柔軟に対応した事業展開と土地の利活用を戦略的に行う必要がある。そのため、造成地の売却だけでなく、賃貸借の手法もうまく活用し、将来の物流やまちづくりにおける環境の変化にも対応できるよう、大阪港湾局として検討すること。
また、港湾は国内外における貨物・貿易の玄関口であり、港湾における国際競争力の強化は、大阪が日本の副首都機能としての役割を果たすための重要なインフラ施設の一つである。そこで、港湾における埋め立て事業を着実に進めて産業用地を期待する企業に応え、大阪港とともに国際競争力の強化に資する施設の整備に加え、ベイエリアの活性化に向けた取組をしっかりと進め、今後の大阪港湾の発展が最大化する方針を検討すること。
(12)大阪府都市基盤施設長寿命化計画の着実な推進
道路や河川、港湾などの都市基盤施設の老朽化率は、今後急速に上昇することが見込まれる。このような中、建設資材や人件費が高騰しているため、定期点検や予防的な補修を通じて施設の寿命を延ばしつつ、突発的な工事需要が発生した場合にも対応できる予算を確保すること。
また、技術職員の減少に対応するため、市町村と連携した若手技術者の育成や大学・民間を活用したスキルアップ支援、定年後も現場対応を希望する人材の積極登用等を行い、人材の育成と技術継承に努めること。加えて、人的リソースの削減が可能な領域ではドローンやAI、センサー技術などを活用し、施設の状態を正確に把握する体制づくりを進めて新技術の活用による点検・管理の効率化を図ること。
(13)空飛ぶクルマの商用化に向けた取組
2025年大阪・関西万博では、「未来社会のショーケース」として空飛ぶクルマの取組が進められている。万博を開催する大阪は、空飛ぶクルマの実用化を先導する都市として相応しい。空飛ぶクルマは都市間移動に革新をもたらし、渋滞緩和や緊急時の迅速な移動、観光資源の拡大、過疎地へのアクセス改善といった多くの社会課題に寄与するものと考える。特に、湾岸地域を中心とした交通課題や関西国際空港、IRなど広域拠点を結ぶ次世代交通インフラとしてニーズが高く、社会実装に最も適したフィールドであると言える。
以上のことから、産学官連携による技術開発や離発着場整備、制度設計のための国への働きかけ等を積極的に行い、全国に先駆けたビジネスモデルを着実に確立すること。
3.子ども輝く未来創造都市・大阪
(1)児童・生徒が自ら主体的に考え、行動する取組の推進
大阪・関西万博では校外学習や特別招待以外にも、イベントや催事への出展、演者としての出演など様々な形で子どもたちが来場している。児童・生徒が万博会場での体験や各種イベント等への参加を通して感じたことや考えたことを仲間とともに振り返り、その成果を発表・共有できる場を提供するなど、自ら主体的に考え、行動する取組をあらゆる機会で取り入れること。
(2)実効性のある府立高校改革アクションプランの策定と着実な実行 ★
公教育では子どもたち一人ひとりの可能性を最大限に伸ばし、最適な学びの機会を公平に保障することが求められる。多様な子どもたちの特性を活かした学びを実現するべく公教育のさらなる充実を図るため、以下に提言する。
授業料無償化の実現により、子どもたちが希望する学校に進学できる可能性が広がった。同時に、子どもたちが「選びたくなる」「通いたくなる」府立高校の質がこれまで以上に重要と認識している。令和7年3月に教育庁が策定した府立高校改革グランドデザインは、多様性に応じた学びや一人ひとりの可能性を最大限伸ばす教育を基本方針に掲げ、個別最適化された学びを尊重する方向性を明示しており、今後の改革の指針として評価している。
現在、同グランドデザインに基づき、今年秋頃を目途に府立高校改革アクションプランの策定が進められている。まずは、教育庁として将来を担う子どもたちの育成に向けてどの様に考えているかを示し、その上で教育庁のビジョンを現場としっかり共有することを前提に、生徒・保護者・教育現場の多様な声を積極的に取り入れた実効性ある内容とするよう強く求める。
また、アクションプランの遂行に必要な財源を確保し、施策の着実な実行と進捗状況の検証、成果の見える化を通じたPDCAサイクルによる継続的な改善を図ること。さらに、通学する生徒の安全・安心の確保や健康の保護、学習意欲向上の観点から、校舎の老朽化対策や防災機能の強化、ユニバーサルデザインに配慮した教室整備など、喫緊の課題に早急に対応すること。
(3)学びの多様化学校の公私連携
不登校になる要因は様々あり、起立性調節障がいや強迫症、適応障がい、発達障がい等の障がいや病状のある生徒への対応が複雑・高度になってきている。今年度、府において公立の学びの多様化学校が開校することになり、すべての生徒に一定水準以上の公平な教育機会が保証されることを期待している。他方、先行する私立の学びの多様化学校は公立に比べて学校ごとに教育目標が明確で、これまでに積み上げた様々な実績や好事例等のノウハウを持っている。また、生徒一人ひとりに寄り添った個別の学習プランを作成するだけでなく、心理・医療の専門的な立場からの視点のもと学習面以外も包括的にサポートされている。
そのため、このような特色あるスタイルを有する私立学校の協力を得て公設民営を含めた運営等も検討しながら、先行する私立の学びの多様化学校と密な連携を取り、生徒が自分に合ったペースで学べる“個別最適な学び”の機会を保障すること。
(4)校内支援ルームにおける適切な人員配置
小中学校では校内支援ルームの数が増えているが、本支援ルームがあっても常に決まった人員の配置が出来ない学校では、生徒に対する対応時間が限られ、また、対応者も毎回変わるため、生徒に寄り添った適切な支援に至りにくいという課題が見受けられる。不登校児童・生徒に必要なことは、安心して相談等ができる信頼関係を築くことである。
そのため、本支援ルームで児童・生徒に応じたきめ細やかな支援ができるよう、支援員等の常駐化や専任化をするなど適切に人材を配置し、子どもたちが安心して学校生活を過ごせる環境を整えること。
(5)児童・生徒への自殺対策
厚労省の「令和6年中における自殺の状況」によると、学生・生徒等のうち小中高生の自殺者数は増加しており、統計がある昭和55年以降で最多となっている。原因・動機別にみると「学業不振」「進路に関する悩み(入試以外)」「学友との不和(いじめ以外)」の順に学校問題は増加している。そのため、教育現場において児童・生徒の自殺対策の推進が急務である。
また、自殺の背景には様々な社会的要因が複雑に関係しているが、児童・生徒に対する孤立対策を進めるとともに、医療・福祉との連携強化、市町村など関係機関との更なる連携を通じて府域全体で児童・生徒の自殺リスクを低下させること。
(6)学校現場でのギャンブル等依存症に対する意識調査と情報周知の徹底
ギャンブル等依存症対策基本法の改正に伴い、オンラインカジノに対する法改正が行われた。予防教育の観点から、まずは、学校現場で児童・生徒や教職員を対象に、オンラインカジノについての意識調査を行うとともに、オンラインカジノをはじめギャンブル等依存症に対する適切な情報周知の徹底を図ること。
(7)教職員間のハラスメント事案への対応体制の強化
教職員間のハラスメントに関する相談が後を絶たず、一部では初動対応の遅れや調査の長期化により、被害を受けた教員が休職を余儀なくされる事例も生じている。こうした状況は、学校現場の信頼を損ね、児童・生徒の学びにも悪影響を及ぼす深刻な問題である。
現在、教育庁では相談体制を整備しているが、外部の専門相談員は主に助言にとどまり、実際の調査や解決には直接関与できない仕組みとなっている。また、相談から解決までの期間が不透明であることも当事者にとって大きな不安要素となっている。教職員が安心して働ける職場環境の整備は、子どもたちへの最良の教育環境をつくる土台となる。
そのため、外部専門家が調査し、関与できる制度の創設並びに対応期間や対応体制の明文化とその運用に加え、相談記録の保存・管理の周知徹底に早急に取り組むこと。
4.誰もが健やかに暮らせる健康寿命都市・大阪
(1)困難な状況にあるこどもや女性、性暴力被害者に対する支援体制の強化 ★
大阪府内には、子どもの貧困やDV・性的暴力を受けた女性、さらには性暴力被害者といった複合的かつ深刻な課題を抱える人々が数多く存在している。近年では、育児放棄といった深刻なケースも報告されており、泉佐野市が独自に「赤ちゃんポスト」の設置を目指すことでも話題になった。これらの問題の背景には、経済的困窮、家庭内不和、暴力や虐待、孤立、社会的支援を要するなどの構造的な要因が複雑に絡み合っている。課題解決に向けた横断的かつ包括的な対応がなされるよう、以下に提言する。
府が実施した子どもの貧困に関する実態調査では、依然として困窮度の高い家庭の存在が明らかになっている。貧困率の高いひとり親世帯に対しては、他の自治体でも実施されている養育費用の立替支援や児童扶養手当の上乗せ支援といった経済的支援を府域の全市町村で実施できるよう支援すること。実態調査で明らかとなった個別の事情に対応できる支援体制を構築するほか、未成年者が闇バイトや売春に巻き込まれないよう官民が連携し、オール大阪で設置している会議体において、根本的な課題解決に取り組むこと。また、地域ごとに子どもが安心して過ごせる居場所や食事提供の拠点を整備し、孤立や虐待の防止につながる包括的な支援を進めること。
DVや性的暴力、育児困難、社会的支援を要するなど様々な困難を抱える女性が支援を必要としており、配偶者暴力相談支援センターの周知を強化するほか、女性相談支援員の全市町村配置を推進し、府域の困難を抱える女性に対する相談支援体制を強化すること。
なお、嬰児遺棄のような痛ましい事件が起きることのないよう、予期せぬ妊娠の相談窓口「にんしんSOS」の一層の周知や、特に支援が必要な妊婦を把握した場合の要保護児童対策地域協議会での見守り、出産後の継続的な支援など、子どもの命を守るとともに、虐待の防止につながる取組を引き続き進めること。
次に、性暴力被害者支援に関しては、ワンストップ支援センターの迅速かつ円滑な支援体制の構築と部局横断的な連携が要となる。医療・警察・福祉・教育等の専門機関との連携を促し、大阪府が主導してワンストップ支援センターの機能強化を図ること。特に今年度は、ワンストップ支援センター事業が委託事業となった初年度である。このことから、有識者検討会議や有識者検討会議医療ワーキングの場で、専門機関の助言や意向を丁寧に聴取するとともに、ワンストップ支援センターの人員配置といった運営体制の状況をしっかりと把握し、持続可能な支援体制の構築を府が中心となって迅速に進めること。
困難な状況にあるこどもや女性の問題は、ひとり親家庭の増加による貧困や養育費用の未払い、家庭内暴力など様々な要因が複雑に絡み合っている。一人でも多くのこどもや女性等の困難な状況が改善されるよう、オール大阪での取組を進められたい。
(2)重大な虐待ゼロに向けた児童福祉行政の水準向上
児童虐待相談件数は全国的に増加の一途をたどっており、府においても高止まりの状況が続いている。こうした中、国の「新たな児童虐待防止対策体制総合強化プラン」において児童福祉司の配置標準が引き上げられたが、府では依然として人員が配置標準に満たず、1人のケースワーカーが多数の案件を抱える厳しい状況にある。
また、児童福祉の第一線を担う人材の専門性確保に向け、スーパーバイザーの育成や中核市での児童相談所・市町村こども家庭センター設置の支援も急務となっている。中核市の児童相談所設置に伴う児童相談所業務の円滑な移行と中核市の支援力向上は、子どもの安全と安心を守り、児童虐待の対応も含めた切れ目のない支援を提供するうえで不可欠である。
そこで、中核市の児童相談所設置による機能移管を単なる権限移譲にとどめず、現場の支援力向上に直結する市職員の専門性の向上を図るための人材育成支援を丁寧に行い、府域全体の児童福祉行政の水準向上を目指すこと。
(3)待たせない診療体制に向けた児童精神医療の体制拡充
発達障がいや情緒的課題を抱える子どもが増加する一方で、児童精神医療の体制は十分とは言えず、診断や治療を必要とする子どもが長期間受診できない状況が続いている。府はこれまで、拠点病院の整備や研修制度を進めてきたが、現場からは「予約が半年先」「継続的に見てもらえない」といった声があり、これらに対応するにはさらなる体制強化が必要である。
待たせない診療体制に向けて、診断・治療の入口を広げて児童精神科や発達外来を有する医療機関を増やし、より多くの子どもが身近な地域で適切な医療を受けられる体制の整備が必要である。府として、市町村や医師会、大学等と連携しながら、広く受診可能な医療提供体制の拡充を進めること。
(4)「大阪依存症センター(仮称)」の早期立上げと支援情報の発信強化
近年、ギャンブル等依存症が社会的課題として深刻さを増している。従来の公営競技やパチンコに加えて急速に普及が進むオンラインカジノ等により、依存症患者は世代や職業を問わず増加傾向にある。これは本人の問題だけでなく、家族関係の破綻や生活困窮、犯罪の温床等社会全体に大きな影響を与えている。
府では、依存症対策拠点「OATIS(大阪依存症包括支援拠点)」をはじめ、医療・相談支援・啓発に取り組んでいるものの、その存在や支援内容が府民に十分に知られていない。そこで、依存症の予防教育や普及啓発、医療体制の整備、治療法の研究、相談支援体制の拡充、人材育成などを体系的に進め「大阪依存症センター(仮称)」を早期に立ち上げること。また、既存の支援策をより効果的に機能させるため、支援情報の可視化と発信強化に取り組むこと。
以上、大阪が日本の依存症支援の先進地となるよう、迅速かつ計画的な体制整備を進め、ギャンブル等依存症に苦しむ当事者とその家族が希望を持てる支援と広報の両輪を強化した総合的な対応を強力に進めること。
(5)医療的ケアを必要とする障がい児者、重度障がい児者への支援の拡充
医療的ケアを必要とする障がい児・障がい者の増加により、支援体制の整備が急務となっている。医療的ケアを担う看護師等の人材不足や重度障がい児者の受け入れが可能な施設の地域偏在、絶対数の不足、ニーズの未充足が懸念されており、実際の利用者数の変動を注視しなければならない。
これらの社会的支援体制の強化のため、看護師バンクのような体制の構築をはかるとともに、地域偏在が著しい重度障がい児者の受け入れが可能な施設について、府域全体のバランスを考慮した整備を進めること。また、医療的ケアを必要とする方の行き場がなくならないよう、医療的ケアのショートステイ受入事業所や医療型短期入所施設事業所の整備が進むよう支援すること。さらに、他府県においても実施されていると聞くが、障がい者の家庭を支えるため、グループホームに入居する障がい者の家庭への家賃補助を検討すること。
(6)障がい福祉サービス事業者に対する運営指導体制の強化
障がい福祉サービス事業者等に対する運営指導の実施率は約7%にとどまっており、単純計算で14年に1回という極めて低い水準となっている。サービスの質の確保や不正行為の防止といった観点から看過できない状況であり、運営指導の実施率向上は喫緊の課題である。障害者総合支援法に基づく「指定受託法人制度」を活用して運営指導の一部を民間に委託し、府は不正が疑われる事業所の監査などに重点的に取り組むという、役割分担を明確にした体制を構築すること。さらに、これらの取組を着実に進めていくため、必要な予算を確保すること。また、令和10年度までに6年に1回のペースで運営指導ができるよう、具体的な対策を講じること。
(7)主任介護支援専門員更新研修の受講要件の緩和
東京都では今年度から主任介護支援専門員更新研修の受講要件を緩和し、現在都内で介護支援専門員として勤務している方も受講できるようにする等、資格継続の拡充に取り組んでいる。このような要件緩和は、国の制度改正を待たずとも府が要綱等を変更するだけで可能である。そこで、現場の実態に即した柔軟な制度設計を行い、意欲ある介護支援専門員の継続的な活躍を支える制度の運用を図ること。
また、主任介護支援専門員更新研修は会場への出席が求められるが、遠方の受講者の負担が大きく、現状でも不足している主任介護支援専門員が減少する一因となっていると聞く。研修をオンラインで実施することにより、受講者の負担軽減を図ること。
(8)がん予防の取組推進及び医療体制の充実と支援
府のがん検診受診率は依然として全国平均を下回っており、府民の健康維持にとって大きな課題である。特に「検診そのものを知らない」「関心がない」といった、いわゆる無関心層の存在が大きく、周知啓発の見直しと受診の動機付けが必要である。そこで、検診の対象となる年齢層に対して周知・啓発の強化を図ること。
また、がんを治療するにあたり、高い治療効果を目指して集学的治療をしっかり提供するほか、病院が相互に連携してがん治療の水準向上に努めるとともに、緩和ケアの充実、在宅医療の支援、がん患者や家族等に対する相談支援、がんに関する各種情報の収集・提供等の機能を備え、地域におけるがん医療の充実に取り組むこと。さらに、先進的かつ低侵襲ながん治療、BNCTの臨床応用を推進するため、医療機関や大学、事業者等の関係機関と緊密に連携し、がん治療法としての普及や認知に努めること。
以上、予防から治療までを切れ目なく支える総合的ながん対策に取り組むこと。
(9)物価高騰の影響を受ける府民への支援
昨今の物価高騰により、特に住民税非課税世帯や年金生活者、子育て世帯を中心に、食料品や光熱費など生活必需品の価格高騰による影響が深刻化している。これらの世帯は収入が限られており、日々の暮らしに大きな困難を抱えている。国や地方自治体において支援策が講じられているものの、依然として支援が届きにくい世帯が存在する。
そこで、今後も食料品や光熱費といった生活必需品に対する支援を継続して実施すること。支援を実施する際には、申請手続の簡素化と情報周知を徹底すること。また、新たな支援の枠組みを設計する際は、対象者の実情に応じたメニューを慎重に検討すること。
(10)府営住宅への子育て世帯の入居促進
国において「こども未来戦略」が制定され、公営住宅への子育て世帯の入居促進等が位置づけられた。府においても、令和6年10月の総合募集から新婚・子育て世帯向けに利便性の高い住戸を重点的に配分するほか、優先入居の対象となる同居する子どもの要件を「小学6年生以下」から「18歳以下」に緩和するとともに、子育て世帯向け住戸や居住環境の整備などが実施されている。
現在、府営住宅では、小学校就学前の子どもがいる世帯を、特に居住の安定を図る必要がある世帯として位置づけ、原則158千円の入居収入基準を214千円に緩和されているが、近年の子育て世帯の経済的負担の増加等を踏まえ、この緩和の対象を18歳以下の子どもがいる世帯にまで拡大するなど、子育て世帯向け住宅支援の充実を検討すること。
(11)エスカレーターの安全利用に向けた取組
エスカレーターは、本来立ち止まって利用することを前提に設計されており、府では、これまでも安全な利用に向けた啓発に取り組むほか、建物所有者等に対して安全対策の実施を呼びかけるなどの対策を行ってきた。引き続き、これらの取組を行って利用者の安全を確保すること。
また、埼玉県や名古屋市では、エスカレーターのより安全な利用のために「エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」が制定されているが、府でも条例制定による効果や課題の収集を行うなど、条例制定の必要性の有無について検討を行うこと。
5.犯罪のない災害・有事に強い安心安全都市・大阪
(1)災害対応の効率化・高度化に向けた防災DX・新技術の活用 ★
南海トラフ巨大地震は今後30年以内に発生する確率が80%程度とされており、いつ大地震が起きてもおかしくない状況にある。直近に発生した能登半島地震の被災地支援を通じて、府内の市町村や関係団体が人的・物的両面から現地に支援を行い、地震への備えの重要性が改めて認識された。この経験や知見を踏まえ、大阪府の「新・地震防災アクションプラン」も一部修正され、特に課題を横断的に解決する手段として、防災DXや新技術の活用が全庁的な取組として位置づけられている。これらの取組については、全部局で知恵を出し合い、速やかに実施してほしい。府域の災害対応力を一層強化するため、以下に提言する。
能登半島地震では困難な状況の中で様々な新技術が活用され、これに習って府でも災害対応の効率化・高度化に向けた新技術の活用検討が打ち出された。山間部のドローン操作による被害状況の把握やカメラを活用した避難所での防犯対策など、あらゆる災害対応で有効と認められる通信技術や機器の活用が進むよう、府職員のデジタルリテラシーを向上させるとともに、全庁を挙げて災害対策関連業務を見直すこと。また、民間企業とのこれまでに結んだ協力体制や連携協定等についても新たな防災技術やノウハウが導入されるよう刷新すること。
地震等の災害発生時に府民や来阪者が防災情報を迅速に収集できるよう、おおさか防災ネットや大阪防災アプリをより使いやすく改善させるとともに、誤情報にも配慮しながらSNS等のツールを積極的に活用すること。加えて、通信機器に不慣れな高齢者や障がい者、災害情報に容易にアクセスできない外国人旅行者等にも防災情報が正確に伝達されるよう、情報収集方法の多重化と周知啓発を継続的に実施すること。
府ではこれまで防波堤の津波震災対策といったハード面での対策により、人的被害9割削減を達成した。しかしながら、死者数を限りなくゼロに近づけるには府民の防災意識の向上といったソフト面での対策が欠かせない。府の広報媒体やイベント等を有効活用して、各家庭での日ごろの備えや迅速かつ安全な避難行動が実践されるよう、「死者ゼロ」の実現をめざした防災啓発を推進すること。
(2)地域防災における多様な防災人材の地域実装と市町村支援体制の強化
府内の防災士は13,000人を超え、大学と連携した養成講座では女性や若年層の参画も進んでいるが、資格取得後の地域実装は依然として課題である。特に防災リーダーの多くは男性であり、避難所運営等における女性の視点が十分に反映されていない。令和6年の能登半島地震では、避難所におけるプライバシー確保・衛生環境・ケア対応の不足が顕在化し、運営体制の多様性と平時からの備えの重要性が改めて示された。
今後は、防災士等の防災人材を中核とした地域防災組織の活性化を進めるとともに、女性に限らず、次世代を担う若者や多様な人材が役割を担える仕組みづくりと制度設計が不可欠である。そのため、市町村における避難所運営マニュアルの整備・見直しに対して府が支援体制を強化するとともに、進捗状況の把握及び改善支援を責任をもって継続的に行うこと。
(3)被災者の「命をつなぐ」ための災害応急対策
近年、南海トラフ巨大地震をはじめとする大規模災害の発生リスクが高まっている。大都市圏である大阪府では、人口の集中と社会インフラの複雑性から災害時の医療対応力が地域全体の被害軽減に直結する。現状、災害時の医療・薬事体制は十分とは言えず、例えば、能登半島地震では医薬品の備蓄情報が不足しており、近隣で調達できたであろうインスリンが手に入らないケースがあったと聞く。また、大阪府北部地震では府保健医療調整本部で活動する災害医療コーディネーターが不足し、活動が長期化した場合のマンパワー不足が生じた。
そこで、地域単位で流通備蓄医薬品の保有量や使用期限等をデータ化して随時共有することにより、災害発生時の迅速かつ的確な供給体制を府域で構築すること。また、災害医療救護体制の中核となる災害医療コーディネーターを養成するための研修を毎年行うほか、薬事分野に特化した研修を行って災害薬事コーディネーターを養成するなど、継続的な人材育成を行うこと。
(4)ブロック塀一般についての安全対策
大阪北部地震を契機に危険と判断されたブロック塀の撤去や軽量フェンスへの改修に対して補助金を交付するなど、安全性向上のための取組が継続的に実施されている。しかしながら、ブロック塀の安全確保は所有者の責任で、点検や改修が十分に行われていないケースや補助制度の存在や申請方法が十分に周知されていないため、制度が活用されていない等の課題がある。引き続き市町村としっかり連携し、重大な事故が起こる前に、危険性のあるブロック塀解消に向けた取組をしっかりと進めること。
(5)「大阪府安全なまちづくり条例」の周知啓発
近年、府内における特殊詐欺被害が急増しており、令和6年は被害額が約61億円にのぼり、過去最悪の被害状況となった。被害防止に向け「大阪府安全なまちづくり条例」を一部改正し、金融機関や事業者、府民への対策を義務化したところである。
そこで、全国初の踏み込んだ改正を行った「大阪府安全なまちづくり条例」について、高齢者のみならず、幅広い世代に周知啓発を行うこと。社会総がかりで防止に取り組む「共助型の仕組み」として整備し、警察、金融機関、コンビニ、教育機関、地域団体など社会全体を巻き込んだ広報啓発と見守りのネットワークを府が中心となって形成していくこと。
(6)無許可営業の風営法違反に対する取締強化
令和7年の風営法改正により、無許可営業を行う店舗への罰則が強化された。法の実効性を確保し公平な営業環境を守るためには、こうした法改正の趣旨を踏まえた厳正な運用が不可欠である。府警においては、引き続き、風俗営業に該当する飲食店の実態把握と許可取得状況の確認を徹底するとともに、無許可営業店舗への重点的かつ厳格な取締を一層強化すること。
(7)自転車等の安全走行に向けた取組
大阪府では、電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車や自転車の事故・トラブルが増加しており、交通ルールの認識不足や利用者のマナー欠如が主な原因とされている。安心・安全な交通環境を守るため、特定小型原動機付自転車や自転車等のルールやマナーの啓発と違法走行の取締強化を進めること。併せて、歩行者や自転車の安全を確保するためにも、青矢羽根型路面標示の設置等、道路交通環境の整備を進めること。
特に自転車について、令和8年4月1日から交通安全の向上とルール遵守の意識を高めるため、信号無視や一時不停止、ながらスマホ、右側通行等の悪質危険な違反に対して交通反則通告制度(青切符)が適用される。本制度導入にあたっては、誤認識や混乱を防ぐため、ルール周知と併せて運用基準などを明確に周知徹底すること。
加えて、本制度は16歳から適用されるため、府内の全高校生に対して、学校の交通安全教室での実演を交えた講習やチラシ・SNSなども活用しながら、対象となる違反行為や反則金額等を広く丁寧に周知啓発すること。
(8)ヘルメットの着用率向上に向けた取組の強化
自転車の事故は、特に子どもや高齢者が頭部損傷により重篤化しやすく、非着用時の致死率は着用時の約2.7倍にのぼる。大阪府内でも、令和6年の自転車事故で、死亡・重傷事故におけるヘルメット着用率はわずか5.5%にとどまり、制度の定着には至っていない。こうした現状を踏まえ、特に交通弱者である子ども・高齢者を守る観点から、以下の取組を進めること。
現在指定されている「Safety Bicycle推進校」29校(7月18日時点)に加え、段階的に全府立高校への展開を図り、生徒のヘルメット着用を含めた自転車安全利用の意識を高めていくこと。府内市町村における補助制度導入状況について把握するとともに、特に、交通弱者である子ども・高齢者に対する無償配布等を含めた支援を検討すること。
春・秋の「交通安全運動」期間に、教育現場・自治体・企業と連携した集中的な啓発を行い、着用の必要性の社会的理解を高めること。併せて、事故多発地域を対象に、地域団体等と連携した啓発活動などの実践的な取組を行い、地域全体の安全意識向上を図ること。
(9)運転免許更新センターの適正配置と府民利便性の確保
大阪府では令和8年度から門真試験場において免許関係事務の一部外部委託を開始し、更新センター整備の段階的推進に着手している。今後、府内に運転免許更新センターを2ヶ所開設するとともに、サブセンターを府内数署に設置する予定であるが、その配置場所と対象エリアについては、地域バランスやアクセス性を考慮した適切かつ効果的な整備とすること。
また、更新拠点が遠方になることによる不便さや、特に高齢者におけるデジタル利用への不安など住民の懸念にも十分に配慮する必要がある。引き続き、利便性の向上とともに住民への周知・理解促進にも丁寧に取り組むこと。
(10)女性警察官に配慮した交番整備
大阪府では交番の老朽化が深刻で、築50年以上や旧耐震基準の施設が多数存在しており、現在、警察機能を最大限に発揮するため、交番等の最適化や機能強化が進められている。
一方で、女性警察官の増加に伴い、更衣室・仮眠室・トイレなどの専門空間が求められるようになったが、旧来の交番では男女共用もしくは男性中心の設計が多く、女性警察官にとって働きやすいとは言い難い環境である。今後、交番の再編整備にあたっては、女性警察官の増員や夜間勤務への対応を見据え、女性専用の仮眠室・専用設備等を備えた交番の増設を計画的に進めること。
また、交番の再編整備にあたっては女性視点を取り入れた施設設計を徹底すること。加えて、既存交番についても女性警察官の受入環境を整備するための改修・改築を速やかに検討すること。
6.産業と自然が豊富で持続可能な都市・大阪
(1)大阪・関西万博を契機としたユニバーサルデザインのまちづくり推進 ★
大阪・関西万博の開催を契機に、年齢、性別、国籍、障がいの有無にかかわらず、誰もが使いやすく安全で快適に暮らせる都市や施設を設計するユニバーサルデザインのまちづくりがいっそう期待される。すべての人が社会参加できる共生社会の実現に向けた環境づくりのため、以下に提言する。
大阪・関西万博は「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマのもと、バリアフリー法や福祉のまちづくり条例に加え、障がい当事者等の声を反映した独自のユニバーサルデザインガイドラインを策定、適用している。会場内では、パビリオン等施設のバリアフリーに加え、感覚過敏や精神的な不安を抱える方のためのカームダウン・クールダウンルームの設置やスマートフォンでQRコードを読み取ると音声で目的地までのルートや距離等を案内する移動支援アプリへの対応など、様々なユニバーサルデザインの取組が随所に見られ、すべての人が安心して楽しめるバリアフリーな万博が実現している。これらの取組を一過性のものとせず、府域全体に波及させなければならない。
そこで、万博での取組を検証しつつ、観光地エリアや大規模駅・地下街といった複合施設、公共交通機関等のバリアフリー化と案内表示や情報提供のユニバーサルデザインの採用をいっそう進めるとともに、建築・設計事業者向けの新たなガイドラインの策定や改定、普及啓発を行うこと。併せて、施設等利用者に対してICT技術を活用した情報発信や行動支援の強化に努めること。
また、現在万博会場では、未来のモビリティ体験としてカメラやセンサー、衛星通信を使用する自動運転技術を活用したEVバスが活躍している。職業運転士不足等による交通空白地のアクセシビリティ向上の観点から、新たな運転技術の社会実装に向けた取組を積極的に推進すること。
(2)2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取組 ★
2050年カーボンニュートラルを実現するためには、技術革新だけでなく社会のしくみや人々の行動変容が必要であり、自治体や民間団体、住民が一体となって取り組まなければならない。クリーンで持続可能な暮らしや環境を次世代に残すとともに、府の地理的優位性や産業集積を活かした関西圏の次世代エネルギーハブとしての機能が確立できるよう、以下に提言する。
大阪・関西万博では「未来社会の実験場」というコンセプトを掲げ、カーボンニュートラルに向けた最先端技術が多数展示、実証されている。例えば、薄くて軽い次世代型ペロブスカイト太陽電池はスマートウェアやバスターミナル屋根に搭載され、作業着のファン駆動やスマホ充電に利用されている。大阪市街地と夢洲を結ぶ水素燃料電池船「まほろば」の運行は、まさにカーボンニュートラルに向けた未来のモビリティ体験であり、今後これらの取組を社会実装へ繋げるための支援が必要となる。
そこで、物流などのカーボンニュートラル化を実現するため、水素燃料電池商用車の導入や水素ステーションの整備を支援するとともに、普及の障壁となっている規制の緩和を国に求めること。併せて、近隣府県市とも連携して、広域的な水素ステーションの整備や運営方法等について検討すること。
新たなエネルギー技術や省エネ、再エネに貢献する取組には、在阪する中小企業やスタートアップを中心に研究開発支援を行うとともに、大阪産業局や商工会議所等とも連携しながら、あらゆる機会を通じてビジネス化を後押しすること。その際は、展示会やマッチング支援、補助制度を拡充しながら段階的な事業化支援の道筋を明確にすること。
加えて、大阪湾岸を起点とした水素やアンモニア、e-メタン、SAF燃料等のサプライチェーン強靭化に向け、次世代エネルギーの供給拠点形成に寄与する事業には、技術開発や商用化実証等に対する支援を積極的に行うこと。
脱炭素社会の実現には府民の参画が欠かせない。アプリ等を活用した事業では、脱炭素行動の「見える化」を行ってポイントを提供するなど参加意欲を高めるインセンティブを付与して個人の行動変容を促進するとともに、府域の市町村や民間団体と連携して廃食用油の回収拠点形成を支援するなどの取組をさらに充実させること。
最後に、関西圏でのエネルギーの安定供給やコスト削減、環境負荷低減を見据え、次世代エネルギーを効率的に管理・利用するためのシステムや拠点整備について、関西広域連合を活用するなどして広域自治体で検討を進め、将来的な連携に向けた具体的なロードマップを示すこと。
(3)プラスチックごみのさらなる削減
大阪・関西万博では、バイオマス由来プラスチックやCO₂、藻・微生物・植物など多様な素材を用いた持続可能な製品や構造物が披露され、プラスチックごみ削減やカーボンニュートラルの実現に資する先端技術が集結した。こうした技術は、脱炭素・循環経済を牽引する大阪発のイノベーションとして、産業・雇用の創出にもつながる。しかしながら、それらの製品には生産コスト等、実用化に至るには課題が多い。このため、出展企業・大学・製造事業者との連携を強化し、大阪産バイオマス製品等の開発・事業化支援を戦略的に進めること。
また、来年開催される「全国豊かな海づくり大会」は、海洋プラスチックごみを社会全体の課題として捉える契機であり、地域間連携と府民意識の転換を促す絶好の機会である。府域全体で課題意識を共有し、各市町村での数値目標設定や府民1人あたりの排出量・回収率の共通指標の導入と見える化を行うなど「万博」「海づくり大会」「SDGs」の理念の実現に向け、府民主体のプラスチックごみ削減の取組を促進すること。
(4)大阪産品のさらなる海外販路開拓の取組
大阪には長年に渡って高度な技術を培い、世界水準の技術力を有する中小企業が数多くあるが、これらの企業の多くはその優れた技術力に見合った販路を十分に確保できていない。特に、大阪・関西万博で大阪の更なる成長に期待が集まる中、海外への販路拡大は喫緊の課題である。一方で、海外販路の拡大については流通課題や販売手数料、ロット確保等、事業者には様々な障壁があるため、海外への事業は安定化を図ることが難しい。
そこで、海外向けに大阪産品の販売を継続的に実現できるよう、グローバルな越境ECなどを得意とする企業との販路開拓事業の取組を進めること。
(5)人材不足を補うための戦略的な取組の推進
今後、更に人材不足が加速する傾向にあることから、労働力人口の変化や労働参加率の変化が経済や社会にどのような影響を及ぼすか、職種別・年代別・職場環境別の供給不足を分析してシミュレーションしなければならない。特に、建設や運輸、介護分野などの生活インフラ職種が深刻で、採用や雇用定着、人材の都市部集中等を考慮した取組が不可欠である。そこで、今後は府内企業における採用後の定着状況を把握・分析し、早期離職者へのフォローアップ支援を実施するほか、離職防止に向けた職場環境改善支援を行うこと。
また近年は、副業・兼業・女性・高齢者・障がい者・外国人など多様な人材の確保の手段として、SNSの活用による積極的な採用が展開されている。このようなSNSでの採用が苦手な中小企業に対しては、大阪産業局の人材採用コンシェルジュ等を活用し、採用広報のスキル研修やSNS運用支援、専門アドバイザーのマッチングを行うなど、実践的な支援体制を構築すること。
(6)府営公園のさらなる魅力向上と「持続成長型の府営公園」に向けたあり方検討
府営公園は、民間活力を導入した魅力創造を積極的に行い、人を呼び込む公園としての活用が進んでいる。このような取組によって収益性の高い公園運営を実現することは、府内各地域の活性化にもつながる。一方で、指定管理者からは各事業実施にあたり、府庁内あるいは関係市町の担当部局との調整を横断的に行わなければならず、手続だけでもかなりの時間的コストが必要との声がある。そこで、民間ならではのスピード感ある投資や運営が発揮できるよう、府が窓口となり、行政サイドの調整や手続きについて一元的に対応できるようにすること。
また、府営公園に民間活力を導入して各事業者が運営努力をすることによって、魅力や集客力が向上する一方で、収益面では様々な課題があり、かつ今後の運営に大きな負担を強いるような管理条件も多くあると聞く。指定管理者の主な収益源は駐車場料金であるが、現在の条例下では柔軟な料金設定ができない。そこで、指定管理者にとってメリットのある料金設定が可能となるよう、例えば、イベントごとに料金を設定できる柔軟な料金体系を実現することや府営公園の利用者にとって普段使いしやすい料金設定などに取り組むこと。
公園への集客施策として園内のイベント実施等があるが、場合によっては占用許可使用料等の負担が必要となる。イベントの性質上、来場者から料金を徴収することが不向きな内容や集客イベントの実施においては、イベント事業者の持ち出し額が非常に大きくなるケースがある。設置許可使用料については、例えば、来場者の利便性向上のために設置する自動販売機は、現在府が公募しており、設置にかかる使用料も府の収入になるなど、指定管理者が柔軟に運営できないことも課題視されている。
このような様々な課題がある中、府営公園のさらなる魅力向上と指定管理者の収益向上と成長の両立が可能な「持続成長型の府営公園」に向けたあり方検討と新たな制度設計に向けた取組を進めること。
(7)万博開催を契機とした都市緑化の推進
大阪では、都市緑化に向けた建築物敷地等緑化促進制度の運用や大阪府森林環境税を財源とした猛暑対策事業が行われている。このような中、現在、万博会場にある「静けさの森」やグラングリーン大阪は大きな反響があり、これらを利用した都市緑化の機運を一層高めるには絶好の機会である。そこで、大規模施設等への緑化基準の見直しなどを検討し、住宅・企業・自治体向けに壁面や屋上緑化等への新たな支援策を検討すること。
また、都市部での緑化を進めていくために、学校の屋上やプールの緑化、校庭の芝生化を推進するなど学校の緑化と教育環境整備の一体的な制度体制の構築を進めるとともに、子供たちが地球環境の保全や生物多様性の保護、防災機能の向上等、緑の大切さを深く学ぶことができるよう学校現場や民間団体、自治体を繋ぐ役割を府が担うこと。
(8)単位面積あたりの農業産出額全国1位への取組
府が単位面積あたりの農業産出額全国1位を目指すには、高付加価値特産品の生産量拡大やブランド力の強化、スマート農業、担い手育成、販路拡大、地域連携等地域に応じた複合的な取組が必要である。府内約330地区で地域計画が策定されたことを踏まえ、産出額の増加に資する先導的な取組への支援を強化するとともに、府内全域への波及を図ること。
また、6次産業化や施設園芸化、農業系企業誘致等を行うことが重要であるが、それには農地の集約が大きな課題である。農地集約に向け、各市町村の地域計画を踏まえた農用地区域と農業関連施設エリアの整理や農業者、自治体、土地改良区が一体となって、地区ごとの土地利用ルールを明確化した上で府として支援を行うこと。
(9)都市型林業の推進と大阪産木材の利活用についての取組
府は都市部に位置しながら北部・南部を中心に森林資源を有し、都市型林業のポテンシャルを有している。しかしながら、林業就業者の高齢化や搬出コストの高さ、市場での需要不足等により、府内林業は衰退傾向にある。特に大阪産の木材利用が進んでいないことから、林業の経済的持続性に向けての取組が重要と考える。
そこで、学校や庁舎、府営住宅など公共施設への大阪産木材の利用を一定義務付けることや府庁内において積極的に大阪産木材を活用すること。さらに、大阪産木材の知名度・ブランド力強化のため、例えば、ネーミング募集等のPRを行うこと。中小企業とのパートナー制度の創設やホームセンターと共同で商品開発を行うなど、供給の仕組みと流通を構築して販路拡大を図ること。
また、林業の人材確保に向けて、高校や専門学校、大学との連携を強化するとともに、働きやすい環境を構築するため、高性能林業機械やICT・AI・ドローン等の最先端機器の導入に対して支援を行うこと。
森林は行政区画に関係なく連続しており山に県境はないという観点から、隣接する京都府・兵庫県・奈良県等との広域的な連携体制を構築し、関西圏における都市型林業の再生と木材の地産地消モデルの確立をめざすこと。
(10)大阪オリジナルぶどう「虹の雫」のブランド価値の確立
大阪のオリジナルぶどう「虹の雫」は50年の歳月をかけた品種改良と栽培実験の末、ようやく市場に送り出せる品質にたどり着いた逸品である。昨年には、百貨店でのPRイベントや南河内地域の直売所でも販売され、今年7月にも新たに百貨店で初売りイベントが行われた。
しかし、「虹の雫」は大阪産果実の中でも希少性が高く、市場での露出が限られていることや新品種であるため消費者や流通業者への認知度がまだ低い。「虹の雫」のような新品種は、早期に積極的な広報を行うことが重要であり、初動的な啓発でのブランド価値確立が消費者の記憶と市場シェアの長期的獲得、ひいては生産者のモチベーションと生産拡大の波に直結する。
そこで、のぼりや印刷媒体、SNS・YouTubeなどのデジタル媒体を活用した広報やアグリツーリズムでの収穫体験等、効果的な情報発信を行うための予算を確保すること。
(11)人と動物が共生できる社会の実現に向けた動物愛護管理行政の推進
【環境農林水産部】
府では、動物愛護、特に多頭飼育崩壊への対策や悪質なペットショップ・ブリーダーの廃業・取締は徐々に強化されている。しかし、今後、行政職員だけでは対応や監視が追いつかない。このため、例えば地域ケアネットワークと連携し、高齢者のペット飼育の把握やペットに関する様々な相談に対する情報発信を行うなど、飼い主に万が一のことが起きた際にペットが路頭に迷わないよう対策を図ること。
また、府では10頭以上飼育する場合に届け出が義務付けられているが、制度の認知度は依然として低い。法改正も見据えつつ、届出の周知徹底や虐待のおそれや周辺住民への生活環境被害がある場合には、行政が立ち入り調査を円滑に実施できるよう関係機関等と連携を密にすること。